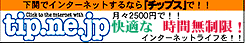|
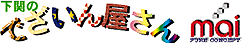 |
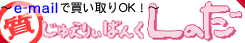 |
|
[小川もこの伝言板一覧に戻る] お名前:ひまつぶし 
地域:中部 音楽のネット配信の特集だった昨夜の「クローズアップ現代」で、 マスターテープを管理する「原盤権」の問題を扱っていましたが、 見ていてすごく気になる事がありました。 CD・ネット配信に関わらず、すべての配布の元となる原盤をレコード会社が持っていると言うことは、 せっかく作った作品なのにアーティストが自由にできないということなのでしょうか。 たとえばレコード会社をクビになっても作品の配布権は返してもらえず、 その作品は闇に葬られてしまったり、 何十年か後に「なつかしの歌」として発売されても、 その収益はアーティストにはいかなかったりといったような。 実際クビになったアーティストが身近にいるので、 この問題はすごく気になります。 ご存知の方、ご意見のある方、 音楽に関わらず文学作品や漫画、コンピュータソフトの世界ではどうなのか。 何でもいいので聞かせてくれませんか。 |
私も詳しくはないのですが。。。
クビになろうが、一旦レコード会社と契約して譲渡してしまった権利は戻らないんじゃないですかねぇ。。
それに、CDって作者以外の人も絡んで制作しますよね。そうの人たちの権利の問題もあるだろうし。
ちなみに、ここの管理人のはまかわさんとお友達のDJソニーさんが
インターネットラジオで音楽が流せないかというのを調べたことがあって、
JASRACさんはストローミングの料金は決めてはいるんですが(クリック数にもよるけど1曲5万円とかそんなの。BGMでも)
それ以外に、著作隣接権っていうのがあってこれはJASRACの管理外なので、無理ですってことでした。
(どうして、FMとかのラジオ放送ではJASRACが一括して徴収してくれるのに、
インターネットラジオは駄目なんだって気がしますが、要はそこまで仕掛けができていないということのようです)
この辺のことは インターネットラジオの評論をしているハックさんがまとめて下さいましたので、参考までに。
http://www.alpha.dti2.ne.jp/~radio/col/ra055.html
http://www.alpha.dti2.ne.jp/~radio/col/ra055_b.html
去年でしたか、朝日新聞の投稿欄(一般投稿欄とは別に)に、あの坂本龍一さんが、著作権についての意見を書いてありました。
そこには、自分で作った作品ながら自分で動かせないことがある、これはおかしい事で間違っている、・・・そういった発言を載せていました。
詳しい内容は忘れてしまいましたし、音楽的な言葉を知らない私だったから、全部は理解できなかったけれど、とても悔しい思いが伝わってきました。
それこそ、坂本氏は、作曲アレンジ、プロデュースも手がける方でしょ!
著作権て一体誰のもの?・・・そんな思いですね。
SAGさん
ハックさんの記事、行ってきました。
著作隣接権ですか。なるほど。
たしかにアーティストだけでCDができているわけではなく、
後ろには大勢のスタッフがいるわけですよね。
確かに忘れてはいけない人だけれど、
「なくてはならない」人ではないですよね。
極端な話、自宅のカセットレコーダーで録音することも可能なわけですし。
詳しくは下に書きますが、
どこか間違っているような気がするのですよ。
ホワイトペーさん
番組のゲストコメンテーターが坂本隆一さんでしたが、
番組の内容自体、業者間の力関係で終わって、肝心の作曲者本人の権利に関してはふれていませんでした。
>著作権って一体誰のもの?
そうですよね。
で、この問題を突き詰めたら、
「製作者の権利を保護するため」という著作権法の意義が根底から揺らいでくるんですよ。
「資本家vs労働者」というマルクス主義を受け継ぐ「ナニワ金融道」の思想で考えてみると、
レコード会社はオリコンという「ただの数字」をエサに人を集め、
契約のことなど何も知らないアーティストから命綱ともいえる著作権を召し上げ、
がっぽり儲けたのち利用価値がなくなったらあっさりと放り出す。
そしてアーティストは裸一貫で路頭に迷い、レコード会社は著作権を振りかざしその後もぼろ儲け。
こういうシナリオがなりたつわけですよ。
アーティストの存在ではなくレコード会社の金儲けを保護するための著作権法。
皆様はどう思われますか?
本人によりコメントは削除されました。 2000年05月12日 18時26分20秒
う〜ん。お気持ちは分かるのですが、
基本的にはアーティストのために著作権があって、セールスの何%という契約になってる訳でしょうから
著作権がなくて一旦レコード会社に納品したら、いくら売れても売れなくても同じ料金っていうのも
むなしいものがありません?
それと
> 「なくてはならない」人ではないですよね。
その人の代わりに誰かが作業しても同じ物ができ上がるとは私には思えません。
それに、自宅のカセットレコーダーで録音したものが、利益を上げるほどのセールスを見込めるかって問題があるのでは?
レコード会社に搾取されるのがいやであれば、インディーズで頑張るという手もあるでしょうし、
そうではなくビックセールスをねらう場合に、ハイリスクハイリターンというのはレコード業界だけではないと思いますし
契約するアーティストがしっかり勉強してから契約にのぞめば、問題ないのでは。。。
私が思うに、著作権があることよりも、JASRACだけで その管理をしていることが問題なのではないかと思います。
アーティストがより自分に利益を運んでくれる代理業者が選べるようになるのが、いいのではと。。
#そうなれば、ネット配信に対する足かせも、競争原理でなくなるかなと。。
この間、某RJ誌なる雑誌に論文を掲載する機会がありましたが...
出版物の世界でも、音楽における「原盤権」的なものが存在します。ですから、私の書いた某RJ誌掲載の論文は、出版社の許可がなければ、いくら書いた本人であっても勝手に使うことはできません。他の雑誌や書籍に転載をするときは、許可が必要になります。もっとも、そういった論文の世界は、他人の論文をパクらない限り、著作権に関してはそんなに厳しくないです(お金にもならないが)。
この投稿に対するコメント |