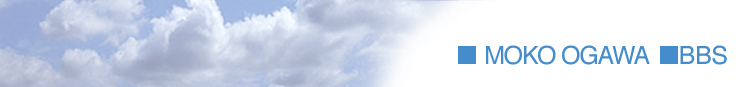
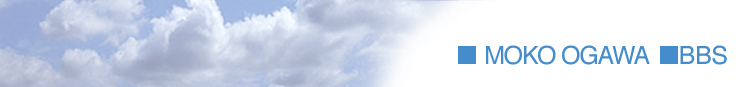 |
| [1] |  | 暴れる・ラヴィーンさん からのコメント(2009年03月01日 18時43分58秒 ) からのコメント(2009年03月01日 18時43分58秒 ) |
| パスワード |
最初に言っておく、 |
| [2] |  | みーつけたっ!さんからのコメント(2009年03月02日 01時13分21秒 ) |
| パスワード |
もこさん、やぁ、がんどぶりです。そしてソルトさん、お久しぶりです!今回のテーマが「ひとり」だって聞いてどうしてもゴスペラーズの名曲、アカペラの素晴らしい「ひとり」を思い出してしまいます。僕だけでしょうか?あの歌もハーモニーが素晴らしいのですがゴスペラーズはこれぐらいにして、 |
| [3] |  | すもっぷ!!さん からのコメント(2009年03月02日 19時55分05秒 ) からのコメント(2009年03月02日 19時55分05秒 ) |
| パスワード |
ひとり。 |
| [4] |  | ゲレーロさん からのコメント(2009年03月03日 17時44分24秒 ) からのコメント(2009年03月03日 17時44分24秒 ) |
| パスワード |
おぉソルトさんがゲストですか。 |
| [5] |  | @!=56さん からのコメント(2009年03月04日 00時28分19秒 ) からのコメント(2009年03月04日 00時28分19秒 ) |
| パスワード |
もこさん、まいどさんです。 |
| [6] |  | その木ぐらしさん からのコメント(2009年03月04日 11時43分04秒 ) からのコメント(2009年03月04日 11時43分04秒 ) |
| パスワード |
その木ぐらし です |
| [7] |  | 南砺福光のもとちゃんさん からのコメント(2009年03月04日 18時31分50秒 ) からのコメント(2009年03月04日 18時31分50秒 ) |
| パスワード |
南砺福光のもとちゃんで〜す |
| [8] |  | 藪林さん からのコメント(2009年03月04日 21時43分52秒 ) からのコメント(2009年03月04日 21時43分52秒 ) |
| パスワード |
@=56さんのリクエストに賛成 |
| [9] |  | はのすけさん からのコメント(2009年03月05日 00時34分02秒 ) からのコメント(2009年03月05日 00時34分02秒 ) |
| パスワード |
もうね、50も過ぎるとですね、一人で居酒屋でもスナックでも何でもござれ。へっちゃらですわ。 |
| [10] |  | バイク乗りのつっちーさん からのコメント(2009年03月05日 03時41分21秒 ) からのコメント(2009年03月05日 03時41分21秒 ) |
| URL=http://baikunori.web.infoseek.co.jp/index.html | ||
| パスワード |
もこさん、こんばんは。 |
| [11] |  | タケゴンさん からのコメント(2009年03月05日 06時31分04秒 ) からのコメント(2009年03月05日 06時31分04秒 ) |
| URL=http://tkg-hus.hp.infoseek.co.jp/ | ||
| パスワード |
家を建て替えたのは「子ども部屋」が無かったためです。 |
| [12] |  | どんがらさん からのコメント(2009年03月06日 03時46分49秒 ) からのコメント(2009年03月06日 03時46分49秒 ) |
| パスワード |
こんにちは |
| [13] |  | いのさんさん からのコメント(2009年03月06日 11時41分14秒 ) からのコメント(2009年03月06日 11時41分14秒 ) |
| パスワード |
・卒業式にひとりは、いる「卒業生起立」の号令に腰を浮かせる保護者。 |
| [14] |  | 神奈川県横須賀市 けふけふさん からのコメント(2009年03月08日 16時18分13秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時18分13秒 ) |
| パスワード |
勉強時間。ひとり旅も好きです。 |
| [15] |  | 兵庫県伊丹市 いるか3さん からのコメント(2009年03月08日 16時18分56秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時18分56秒 ) |
| パスワード |
一人が良いのは近所の温泉に行く時。 |
| [16] |  | 秋田市 ゴットゥさん からのコメント(2009年03月08日 16時19分46秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時19分46秒 ) |
| パスワード |
心地よいのは 一人ショッピング。 |
| [17] |  | 福岡市 亜季さん からのコメント(2009年03月08日 16時20分18秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時20分18秒 ) |
| パスワード |
勉強位しか一人でいられない。 |
| [18] |  | 長野県駒ヶ根市 志乃さん からのコメント(2009年03月08日 16時20分51秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時20分51秒 ) |
| パスワード |
暮らす。結婚して旦那と暮らすのも大変だと感じています。所詮他人ですもんね。 |
| [19] |  | 静岡市 正広さん からのコメント(2009年03月08日 16時21分15秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時21分15秒 ) |
| パスワード |
一人がいいのは映画・音楽・ライブ鑑賞や趣味の時間。好きな事は独りで愉しみたいですね。 |
| [20] |  | 京都府舞鶴市 岸代さん からのコメント(2009年03月08日 16時21分50秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時21分50秒 ) |
| パスワード |
勉強はひとりのほうが効率が上がる。 |
| [21] |  | 茨城県鹿嶋市 マリオネットさん からのコメント(2009年03月08日 16時22分21秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時22分21秒 ) |
| パスワード |
暮らす。介護保険の世話になるようになってから死について考える様になったので |
| [22] |  | 沖縄県那覇市 美咲さん からのコメント(2009年03月08日 16時22分45秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時22分45秒 ) |
| パスワード |
|
| [23] |  | 福島市 仁美さん からのコメント(2009年03月08日 16時23分15秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時23分15秒 ) |
| パスワード |
映画・音楽・ライブ鑑賞や趣味の時間。日々家事・育児に追われてるので自分の趣味は一人がいいです! |
| [24] |  | 群馬県富岡市 わんちゃんさん からのコメント(2009年03月08日 16時23分46秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時23分46秒 ) |
| パスワード |
暮らす。24時間自分の好きなように暮らせるから. |
| [25] |  | 名古屋市 お豆の彼女はしずくちゃんさん からのコメント(2009年03月08日 16時24分16秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時24分16秒 ) |
| パスワード |
勉強。他にもいくつかひとりのほうがいいものはありますが、やはり、1つ選択するなら、集中が大切な勉強ですね。 |
| [26] |  | 横浜市 美夏さん からのコメント(2009年03月08日 16時24分41秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時24分41秒 ) |
| パスワード |
一人外食、ファースフード位ならできます。 |
| [27] |  | 宮城県仙台市 さやままさん からのコメント(2009年03月08日 16時25分05秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時25分05秒 ) |
| パスワード |
孤独を感じるのは、恋人にフラレて落ち込んでるのに友達の誰とも都合が合わなかったとき。 |
| [28] |  | 新潟市 スタバ大好きさん からのコメント(2009年03月08日 16時25分30秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時25分30秒 ) |
| パスワード |
一人では抵抗があって、外食はできません。お腹がすいても家まで我慢。一人で出来るのはスタバかドトールだけ。 |
| [29] |  | 愛知県安城市 あきぽんさん からのコメント(2009年03月08日 16時26分08秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時26分08秒 ) |
| パスワード |
一人が良いのは勉強。主人と好きな番組の趣味が合わないため。 |
| [30] |  | 横浜市 よーチャンさん からのコメント(2009年03月08日 16時26分37秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時26分37秒 ) |
| パスワード |
孤独を感じるのは 病気をして一人で一日中寝ていても誰も来ない時。 |
| [31] |  | 鹿児島市 ちゃこさん からのコメント(2009年03月08日 16時27分07秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時27分07秒 ) |
| パスワード |
買い物は絶対一人の方がいいです!人に気を遣わずに自分のペースで色々好きなだけ見て回れますから。 |
| [32] |  | 山形県東田川郡 秀穗さん からのコメント(2009年03月08日 16時27分36秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時27分36秒 ) |
| パスワード |
一人が良いのは映画・音楽・ライブ鑑賞や趣味の時間。群衆の中の孤独が味わえます。市中徘徊も楽しいです。 |
| [33] |  | 広島市 RKさん からのコメント(2009年03月08日 16時28分03秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時28分03秒 ) |
| パスワード |
ファーストフードやコーヒーショップには行けます。 |
| [34] |  | 大阪府和泉市 里美さん からのコメント(2009年03月08日 16時28分44秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時28分44秒 ) |
| パスワード |
一人牛丼・カレー・立ち食いそばまでOK。一年間中華料理屋に通ったことありますよ。 |
| [35] |  | 東京都板橋区 文子 さん からのコメント(2009年03月08日 16時29分20秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時29分20秒 ) |
| パスワード |
一人がいいのは暮らす。買い物に行くとき等は特にそう感じます。 |
| [36] |  | 石川県加賀市 英樹さん からのコメント(2009年03月08日 16時29分46秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時29分46秒 ) |
| パスワード |
一人焼き肉できます。わいわいとはまたちがった感覚がいいですからひとりやきにくにも是非チャレンジしましょう。 |
| [37] |  | 岐阜市 じゅんさん からのコメント(2009年03月08日 16時30分14秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時30分14秒 ) |
| パスワード |
一人でファーストフードやフードコートでの食事までなら出来ます。 |
| [38] |  | 東京都葛飾区 悠人さん からのコメント(2009年03月08日 16時30分41秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時30分41秒 ) |
| パスワード |
映画・音楽・ライブ鑑賞や趣味の時間。でもやっぱり一人はさみしい。 |
| [39] |  | 横浜市 ギスケさん からのコメント(2009年03月08日 16時31分06秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時31分06秒 ) |
| パスワード |
一人居酒屋、一人カラオケもOK。 |
| [40] |  | 群馬県前橋市 美佐子さん からのコメント(2009年03月08日 16時31分32秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時31分32秒 ) |
| パスワード |
勉強は一人が一番集中できます。 |
| [41] |  | 大阪府堺市 うめさん からのコメント(2009年03月08日 16時32分00秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時32分00秒 ) |
| パスワード |
一人牛丼・カレー・立ち食いそばまでOK。 |
| [42] |  | 横浜市 泉さん からのコメント(2009年03月08日 16時32分39秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時32分39秒 ) |
| パスワード |
一人では抵抗があって、外食はできません。 |
| [43] |  | 茨城県鹿嶋市 キクコさん からのコメント(2009年03月08日 16時33分03秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時33分03秒 ) |
| パスワード |
一人が楽しいのはショッピング。 |
| [44] |  | 富山市 修子さん からのコメント(2009年03月08日 16時33分39秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時33分39秒 ) |
| パスワード |
居酒屋は×ですがカラオケは○です。 |
| [45] |  | 札幌市 育子さん からのコメント(2009年03月08日 16時34分08秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時34分08秒 ) |
| パスワード |
一人旅が大好き。一人焼き肉できます。1人でも全然気になりません。 |
| [46] |  | 広島市 香代子さん からのコメント(2009年03月08日 16時34分37秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時34分37秒 ) |
| パスワード |
|
| [47] |  | 島根県松江市 隆司さん からのコメント(2009年03月08日 16時35分07秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時35分07秒 ) |
| パスワード |
勉強部屋が欲しいです。 |
| [48] |  | 名古屋市 ちいままさん からのコメント(2009年03月08日 16時35分41秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時35分41秒 ) |
| パスワード |
一人が良いのは暮らす。一人暮らしの経験がないから、ない物ねだりかなぁ〜!? |
| [49] |  | 大分市 FNさん からのコメント(2009年03月08日 16時36分11秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時36分11秒 ) |
| パスワード |
1人で出かけるのが好きです |
| [50] |  | 長崎県西彼杵郡 りさぷさん からのコメント(2009年03月08日 16時36分38秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時36分38秒 ) |
| パスワード |
一人が良いのは買い物。相手が気になって、集中できず、結局何も変えないこともある…。 |
| [51] |  | 愛知県刈谷市 スプーンおばさんさん からのコメント(2009年03月08日 16時37分07秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時37分07秒 ) |
| パスワード |
買い物ですね。もうかれこれ7年ほど1人で買い物に行ったことはなく、子連れです。久しぶりにひとりでゆっくりショッピングしたいなァ。 |
| [52] |  | 愛知県豊田市 裕子さん からのコメント(2009年03月08日 16時37分39秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時37分39秒 ) |
| パスワード |
一人牛丼・カレー・立ち食いそばまでOK。お茶するのが好き。 |
| [53] |  | 東京都世田谷区 ユミコさん からのコメント(2009年03月08日 16時38分11秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時38分11秒 ) |
| パスワード |
旦那の寝相が悪いので寝るのは一人がいいです!! |
| [54] |  | 神奈川県川崎市 セキセイインコさん からのコメント(2009年03月08日 16時38分37秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時38分37秒 ) |
| パスワード |
一人焼き肉できます。 |
| [55] |  | 愛媛県松山市 ラジオネームアキさん からのコメント(2009年03月08日 16時39分06秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時39分06秒 ) |
| パスワード |
一人が良いのは映画・音楽・ライブ鑑賞や趣味の時間。旦那や子供が寝てからビールを飲みながら録画したテレビ番組やDVDを見るのは最高の楽しみです。 |
| [56] |  | 千葉県市原市 メル郎さん からのコメント(2009年03月08日 16時39分35秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時39分35秒 ) |
| パスワード |
出張先での昼食。他人のこと気にせず自分の好きなもの食べる方が気楽。 |
| [57] |  | 千葉県船橋市 幸子さん からのコメント(2009年03月08日 16時40分01秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時40分01秒 ) |
| パスワード |
一人が良いのは勉強。図書館では絶対に勉強できません。 |
| [58] |  | 大阪市 ノマドさん からのコメント(2009年03月08日 16時40分31秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時40分31秒 ) |
| パスワード |
映画・音楽・ライブ鑑賞や趣味の時間は所謂「〜しながら」がしにくく一人のほうが集中できますね。 |
| [59] |  | 北海道江別市 薫子さん からのコメント(2009年03月08日 16時41分03秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時41分03秒 ) |
| パスワード |
一人旅が好きでしょっちゅうしてました。 |
| [60] |  | 大阪府大東市 恵美さん からのコメント(2009年03月08日 16時41分29秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時41分29秒 ) |
| パスワード |
映画は一人の方が集中できます。 |
| [61] |  | 大阪府東大阪市 弘子さん からのコメント(2009年03月08日 16時42分00秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時42分00秒 ) |
| パスワード |
勉強は独りじやないと気が散ってできない。 |
| [62] |  | 埼玉県さいたま市 C21KYさん からのコメント(2009年03月08日 16時42分29秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時42分29秒 ) |
| パスワード |
ツマミは自分で作って酒を飲んでいます。 |
| [63] |  | 広島県廿日市市 えれはいむさん からのコメント(2009年03月08日 16時42分59秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時42分59秒 ) |
| パスワード |
一人でいるのは好きだけど、食事とかは一人で行くと、周りの目が気になるから行かないかな〜。 |
| [64] |  | 埼玉県さいたま市 美紀さん からのコメント(2009年03月08日 16時43分25秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時43分25秒 ) |
| パスワード |
一人では抵抗があって、外食はできません。いまだに一人でマックなど食べに行けないです。 |
| [65] |  | 富山県高岡市 キューピーさん からのコメント(2009年03月08日 16時44分00秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時44分00秒 ) |
| パスワード |
一人が良いのは映画を観るとき。子供と一緒に映画鑑賞してると、話しかけてくるので、聞き逃しがあるから。 |
| [66] |  | 兵庫県姫路市 のんきさん からのコメント(2009年03月08日 16時44分29秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時44分29秒 ) |
| パスワード |
経験上勉強の時は一人がベストです。 |
| [67] |  | 埼玉県越谷市 TADさん からのコメント(2009年03月08日 16時44分58秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時44分58秒 ) |
| パスワード |
勉強は一人に限ります。複数でやるとどうしてもレベルの低い方にあわせざるをえないので、効率がよくないです。 |
| [68] |  | 東京都世田谷区 勝生さん からのコメント(2009年03月08日 16時45分26秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時45分26秒 ) |
| パスワード |
一人が良いのは、お風呂にはいってリラックスして音楽を聴くとき。 |
| [69] |  | 静岡県藤枝市 みどりさん からのコメント(2009年03月08日 16時46分02秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時46分02秒 ) |
| パスワード |
一人のほうが気が楽とか楽しめる事は確かにあるので、それを重視する場面があるのはいいことだと思います。ただ生活全てを一人よがりに過ごしてきた人は、病気になった時頼れる人もなく身内からも迷惑がられるケースが、病院でも非常に多く見られるようになってきています。一人を尊重して生きるならば、どんな状況になっても対処できる準備を整えておくべきだと思います。 |
| [70] |  | 愛知県一宮市 ちーちゃんさん からのコメント(2009年03月08日 16時46分29秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時46分29秒 ) |
| パスワード |
一人牛丼・カレー・立ち食いそばまでOK。一人でも平気ですが、やっぱり主人と一緒がいいですね! |
| [71] |  | 鹿児島県姶良郡 ひなたぼっこさん からのコメント(2009年03月08日 16時46分57秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時46分57秒 ) |
| パスワード |
集中したい趣味の時間は一人のほうが断然楽しめます。 |
| [72] |  | 岡山県備前市 ゆみ子さん からのコメント(2009年03月08日 16時47分30秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時47分30秒 ) |
| パスワード |
暮らす。 |
| [73] |  | 富山県南砺市 @!=56 さん からのコメント(2009年03月08日 16時48分04秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時48分04秒 ) |
| パスワード |
確かに、勉強、それも新しいことや、苦手なことを克服しようと言う時は、独りのほうが定着が早い。 |
| [74] |  | 富山市 もえぎさん からのコメント(2009年03月08日 16時48分36秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時48分36秒 ) |
| パスワード |
映画や音楽ライブなどは二人で行ったほうが喜びを分かち合えるのでGOODなんですが 私の趣味は「ひとり」で充分出来る事なんで、一人がいいかな〜。 |
| [75] |  | 富山県南砺市 ゴンザレスどんぶりさん からのコメント(2009年03月08日 16時49分11秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時49分11秒 ) |
| パスワード |
読書は独りがいいです。息子達への読み聞かせも楽しいですが、それだけでは、読むものが偏ってしまいますから・・・ |
| [76] |  | 富山市 婦中のアキちゃんパパさん からのコメント(2009年03月08日 16時49分40秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時49分40秒 ) |
| パスワード |
一人は、つまんないですよね。映画を見たり、コンサート行ったりしても共感できる相手が、欲しいですよね。 |
| [77] |  | 富山県射水市 三姉妹のママさん からのコメント(2009年03月08日 16時50分11秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時50分11秒 ) |
| パスワード |
映画はやっぱり一人の方が気が楽です。周りを気にせずに泣く事ができますから(笑) |
| [78] |  | 群馬県太田市 文夫さん からのコメント(2009年03月08日 16時50分44秒 ) からのコメント(2009年03月08日 16時50分44秒 ) |
| パスワード |
個人的な買い物は(服とか)は1人のほうがいいです。 |
| 【 小川もこの伝言板 一覧に戻る 】 |
|
| ◇Copyright(C) 2000-2008 Tips. All Rights Reserved.◇ DB-BBS-system V1.29 by Rapha. |