吉田兄弟さんの件について
はのすけさんの書かれたこと、うなづくところが多いのですが、それをいっちゃおしめぇよ、と、いにしえの正月映画の主人公にあやうくなってしまいそうになりまして。
まだまだこれからの音楽家で、色々意欲的な試みはして見るべきだと思いますし、したがって、洋楽器と和楽器の合奏も色々試した方が宜しいかと思いますが、
少なくとも、現状、最近の2枚ほど聴かせていただき、2点ほど、門外漢且素人目(耳)からきになったことをば。
それが旋律の体系からくるものなのかは分かりませんが、聞き手が「津軽三味線」に期待するものが薄い、ということ。青森以外にいる者と、青森で育った方の「津軽三味線」観に違いがあるのかもしれませんが、それは、上の書き込みで書いたとおり、冬の波濤と吹雪の中で立地尽くす生命力であり、あるいは和楽器である以上、深深と降る雪の中にさす紅い椿の花の淡彩的な凛とした佇まいであるはず、だという思い込みが聞き手にはある。その思い込みを覆すところまでにはまだ至っていないように思われる。
もうひとつは、ひょっとしたら、ミキシングの工夫一つで解決するのかもしれないが、吉田兄弟名義である以上、太棹が主、他の楽器が客あるいは副であるはずなのが、残念ながら、主のほうがともすれば埋もれがちな印象があります。
津軽三味線というのは、情念というものがかなり直裁的に現れるものであり、奏法、アレンジというのは、それを補助するものではないかと想像するに、その上で、個人的な希望を申し上げるならば、異種格闘技的楽曲というのは、自身の三味線と同様、他の楽器の研究も必要になってくる。勿論それは必要であるのだろうけれど、それよりも、込める情念の質についてもっと拘って欲しいような気がします。
はのすけさんが揚げておられる東儀秀樹さんや山本邦山さんの楽曲にしても、スマートなのはよいとしても、2,3曲聴けば、もう充分、となってしまうのは、込められた情念が、その実、巷の我々とそう差がない、本質的にはそこに新しい世界を感じられないから、というところに問題があるように思われます。
とはいえ、イメージとして、決して横文字になるべきではないとしても、現代のレイアウトで、現代のスマートな書体で書き表そうとする試みすべてがムダだとは思いませんので、2作3作後のを期待したいと思います。
|
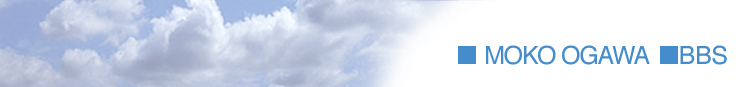
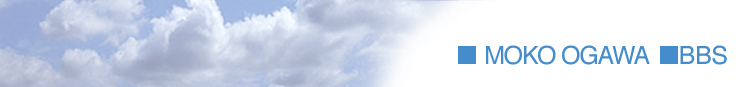

 からのコメント(2008年12月21日 21時47分50秒 )
からのコメント(2008年12月21日 21時47分50秒 )
 からのコメント(2008年12月22日 21時59分55秒 )
からのコメント(2008年12月22日 21時59分55秒 )
 からのコメント(2008年12月23日 09時50分24秒 )
からのコメント(2008年12月23日 09時50分24秒 )

 からのコメント(2008年12月26日 11時44分08秒 )
からのコメント(2008年12月26日 11時44分08秒 )
 からのコメント(2008年12月29日 17時04分32秒 )
からのコメント(2008年12月29日 17時04分32秒 )
 からのコメント(2008年12月31日 22時26分06秒 )
からのコメント(2008年12月31日 22時26分06秒 )
 からのコメント(2009年01月01日 18時42分53秒 )
からのコメント(2009年01月01日 18時42分53秒 )
 からのコメント(2009年01月01日 19時00分25秒 )
からのコメント(2009年01月01日 19時00分25秒 )
 からのコメント(2009年01月01日 23時49分15秒 )
からのコメント(2009年01月01日 23時49分15秒 )
 からのコメント(2009年01月01日 23時58分09秒 )
からのコメント(2009年01月01日 23時58分09秒 )
 からのコメント(2009年01月02日 05時41分21秒 )
からのコメント(2009年01月02日 05時41分21秒 )
 からのコメント(2009年01月02日 08時45分49秒 )
からのコメント(2009年01月02日 08時45分49秒 )