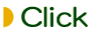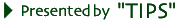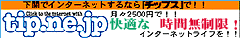「裁き」ということは一種類ではないと思います。
一つ目は「統治者」(実際の遂行者は国家権力を有する存在だが、その主体は主権者たる国民であることを原則とする)からみたものです。
多くの国は「法律」によって統治される「法治国家」という形態をとってます。
現在の裁判はその法律を破ったことに対して行われます。
裁かれて「罪」があると判断された者に対して「罰」が与えられるのです。
この一連のシステムは何のために行われているかというと、それは「秩序」を守る事です。
秩序を乱す者が現れる事を防ぎ、また、乱した者が再び秩序を乱すことがないようにするのです。これは抑止力といえるでしょう。
その裁判によって下される「罰」について、ある国の判断ではその抑止力を発揮するために死刑が必要であると認め、ある国では認められない・必要ないという状況なのだと思います。
(いわゆる「刑事」ですね)
もう一つは「被害者」からみたものです。
この場合の「裁き」は、わかりやすく言えば加害者には被害者に与えた苦痛・被害に相当する負荷を与えることを罰とすることです。
その目的は加害者から被害者への「償い」です。
通常は損害賠償という形で行われます。
(これは「民事」ですね)
つまり「死刑」を行うかどうかは「統治者」が「秩序」維持できるかどうかが基準であり、それが「被害者」の立場を必ずしも考慮に入れたものではないのですね。
だから遺族が死刑の執行を望んでいなくても死刑は執行されるし、逆に死刑を望んでいても死刑が執行されないこともあるわけです。
とはいえ「死刑」行うかどうかについて「被害者」の意志を全く無視していいのか?感情的には無視できないのですが、人の命に関わることなのでどうしてもシステムのルールを遵守しなくてはならないというのが現実なのでしょう。
僕には「死刑」の存在に「抑止力」の効果があるのかは分かりません。
まして今回の事件は逆に「死刑になるために」発生した可能性すらあります。
この場合はたとえ何があろうと防ぐことが出来ませんでしょう。
また、どんな償いをしても被害者が癒されることはないと思います。
ぼくは「裁き」にもう一つ、「加害者」からみたものがあると思います。
所詮「人が人を裁く」ということには限界があります。
たとえどんな「罰」を科されようとも、どんな「損害賠償」を要求されようとも、加害者に罪の意識が無かったり稀薄だったりしたら、それは本当に裁かれていると言えるでしょうか。
「加害者」を本当に「裁く」事が出来るのは、その加害者が自らの心の中に持つ「法」のみだと思います。
そもそも「善悪」ということ自体が人間だけがその社会生活の中で作り上げた観念です。
だから時代や場所で善悪の基準も違っています。
そしてそれは人間の心の中で作られたものです。
「法律」などは各個人の中にある「法」が最大公約数的に明文化されたものといえます。
しかし、その基準は各個人によって違っています。
だから「法律」に照らして裁けば「有罪」であっても、各個人の「法」では「悪くない」と判断される事も起こるでしょう。
これでは「加害者」が反省することなど期待できません。
死刑が存在したとしても抑止力になりません。
被害者は決して癒されないことでしょう。
オクラホマの場合も、犯人が死刑執行前に被害者の神経を逆撫でするようなことを言いかねないので死刑に立ち会わないと言う人もいましたね。
すべての人が納得する「裁き」。
「裁き」の基準である「善悪」が人が作り出したものである以上、それは永遠に無理なのかもしれません。
とはいえ、理想に近づく努力だけは進めて行くべきでしょうね。
そのためには「統治者」が「法律」の「秩序」を守るために「裁判」を適正にしていくだけでなく(どういう制度が理想かはよく分かりませんが)、各個人が持つ「法」が大きく外れた人間の出現を防ぐこと。仮に現れたとしても、その犯人の大きく外れた「法」を何らかの方法で修正することではないかと思ってます。
これは「抑止力」だけでなく、被害者の「癒し」にもつながると思います。
|