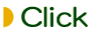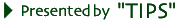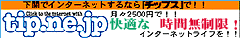建国記念の日、私の地元では毎年、「奉祝会」と「考える会」が開催されています。
私の記憶だと「四方拝」(元旦)、「紀元節」(建国記念の日)、「天長節」(前の天皇誕生日、みどりの日)、「明治節」(明治の天皇誕生日、文化の日)だったような気がしますが。
建国記念の日はは「紀元節」と言ったらしく、これは最初の天皇、神武天皇の即位の日を表したらしい、と言う事だけだったんですが、調べてみると結構奥が深いようです。
最初の天皇、神武天皇は日本書紀や古事記の中に出てくる最初の天皇で、日本書紀上では天照大神の曽孫(ひ孫)とされています。即位したのは紀元前660年に当たるそうです。即いた年を皇紀元年としています。この皇紀と言う言い方、戦前まではちょくちょく見掛けたんじゃないかと。今はすっかり見掛けませんが、神事(神社の儀式や催し)の時には結構使われたりするようです。ちなみに紀元2600年が昭和15年でしたから、今年は2661ですね。「紀元2600年」とか云う国民歌が出回ったそうです。
2/11が紀元節と制定されたのは明治7年(1874)です。最初(明治5年11月)は、旧暦1/1を新暦換算して1/29にしたんですが、後年(明治7年10月)改めて逆換算してみたところ、2/11が正しいと言う事になったようです。こうして「紀元節」が誕生しました。四大節の一つとして、戦中まではよく言われたみたいです。
これが昭和23年、祝日法の公布により廃止され、昭和41年の法改正に合わせて復活、「建国記念の日」とされました。これが今まで続いてるワケですね。
私見として...(デーヴ川崎さんの居酒屋に書くような意見ですが)、日本の神話教育を過去の不幸な歴史と結びつけ天皇の神格化につながると云い行わず、外国の神話を教える今の世の中、不思議に思います。
なんか、議論を醸し出しそうになりましたが、その場合はここじゃなく居酒屋で議論しましょう。
|